宝塚歌劇団雪組の男役スターとして輝く縣千さん。
172cmの高身長と端正なビジュアル、そしてダイナミックなダンスで多くのファンを魅了し続けています。
2015年に101期生として入団し、「雪組の御曹司」とも呼ばれる彼女ですが、その魅力的な人格の根源には、温かく愛情深い家族の存在があります。
特に注目すべきは、芸名「縣千」の由来です。
本名の「千」と、幼い頃に家族と参加した地元宇治市の「あがた祭り」から名付けられたこの芸名には、家族との深い絆と大切な思い出が込められています。
今回は、縣千さんを育んだ家族について、母親との関係、兄弟とのエピソード、そして実家での成長過程を詳しく探っていきます。
1. 縣千さんの実家・出身地について
縣千さんは京都府宇治市で生まれ育ちました。
本名は小林千里(こばやし ちさと)さんで、府立莵道高等学校を卒業後、宝塚音楽学校へと進学されています。
宇治市といえば平等院鳳凰堂や宇治茶で有名な歴史ある街ですが、縣千さんにとって特別な意味を持つのが、毎年6月5日から6日未明にかけて行われる「県祭り(あがたまつり)」です。
この祭りは縣神社で行われる「暗夜の奇祭」として知られ、深夜に沿道の灯火をすべて消した暗闇の中で神輿が練り歩く神秘的な祭りです。
毎年12万人以上の人々が訪れる宇治市の代表的なお祭りで、縣千さんの家族もまた、幼い頃から毎年参加していたようです。
芸名の「縣千」は、この家族との思い出深い「あがた祭り」と、本名の「千」を組み合わせて名付けられました。
縣千さん自身も「潔い名前がいいなと思って決めた。自分だけの『あがた色』を大事にしていきたい」と語っており、家族との絆を大切にする気持ちが伝わってきます。
実家の詳しい情報は公表されていませんが、一般家庭よりは裕福である可能性が指摘されています。
ただし、父親の職業などについては一切明かされておらず、縣千さんも家族のプライバシーを大切に守っている様子がうかがえます。
共働きのご両親のもと、4人家族で育った縣千さんの家庭は、愛情に満ちた温かい環境だったことが、様々なエピソードから読み取れます。
2. 母親からの愛情と人生指針
縣千さんの人生に最も大きな影響を与えているのが、母親から受けた重要な言葉です。
それは「自分のやりたいことをやりなさい。やり切ったかどうか考えなさい」という、シンプルでありながら深い意味を持つメッセージです。
この言葉について、縣千さんは非常に印象的なエピソードを明かしています。
公演の合間の休みに楽しそうなことを見つけると、好奇心旺盛な縣千さんは「もしかしたら劇場の外に新しい人生があるんじゃないか」と思ってしまうことがあるそうです。
そんな時、母親が昔から変わらず「やりたいことをやりなさい」と言ってくれるのですが、その後には必ず「やり切ったかどうか、考えなさい」という言葉が続きます。
この言葉を聞くと、縣千さんは「まだまだ私は男役をやり切っていないな」と気づき、あっちこっちに動いていた心が宝塚の舞台へと戻ってくるのだそうです。
母親の言葉は、縣千さんにとって人生の道しるべとなっており、現在もなお彼女を支え続けています。
母親の教育方針は「時に自由に、時に厳しく」というものでした。
縣千さんの好奇心旺盛で自由奔放な性格を「いいね、楽しそうだね」と褒めて伸ばしてくれる一方で、家の真っ白な壁にクレヨンで大作を描き上げたときだけはしっかりと叱られたというエピソードも残っています。
この絶妙なバランス感覚が、縣千さんの現在の人格形成に大きく貢献しているのは間違いありません。
好奇心の赴くまま動き回る自分の心をちゃんと認め、同時に母親の言葉もしっかりと受け止める素直さは、まさに「家族の中で培ったもの」だと縣千さん自身も語っています。
3. 4歳年上の姉との特別な関係
縣千さんには4歳年上のお姉さんがいて、彼女の人格形成に極めて重要な役割を果たしました。
共働きで忙しいご両親に代わって縣千さんの面倒を見てくれたのがこのお姉さんで、まさに第二の母親のような存在だったのです。
お姉さんは縣千さんに対して、「されて嫌なこと、怒ること、悲しいこと」など、人として基本的なマナーや道徳を厳しく教え込みました。
縣千さんは「その姉が人はこれをされたらイヤなんだよ、怒るんだよ、悲しいんだよと、私に厳しく叩き込んだのが『人として』の基本でした」と振り返っています。
この教育は時として厳しすぎることもあり、あまりの厳しさに姉妹喧嘩になることもあったそうです。
しかし縣千さんは「いつもすぐそばに『教えてくれる人』がいたことには感謝しています」と語っており、お姉さんへの深い感謝の気持ちを表しています。
4歳という年齢差は、幼少期においては非常に大きな差です。
お姉さんは縣千さんにとって身近な大人として、社会性や人間関係の基本を教える重要な役割を担っていました。
この経験が、現在の縣千さんの思いやり深い人柄や、周囲の人々との良好な関係性の基礎となっているのです。
家族構成は、ご両親と4歳年上のお姉さん、そして縣千さんの4人家族でした。
父親の詳しい情報は一切公表されていませんが、共働きで家族を支えながらも、娘たちの成長を温かく見守る愛情深い父親だったことが想像されます。
4. 幼少期のエピソードと家族の影響
縣千さんの幼少期は、好奇心旺盛で多彩な趣味に満ちた日々でした。
特に印象的なのが石ころ集めへの情熱で、この趣味が高じて鉱物標本を作ったり、各地の鍾乳洞を訪れたりするほどでした。
河原や海辺に落ちているものから、ミネラルショーで気に入って購入したものまで、あらゆる石を集めていたそうです。
縣千さん自身も「一つのことにとことん打ち込むところがあり、子供のころは大好きな石ころ集めが高じて鉱物標本を作ったり、各地の鍾乳洞に行ったりしていた」と振り返っており、何事にも全力で取り組む性格が幼少期から現れていたことがわかります。
また、部屋にこもって絵を描くことに没頭する日もあれば、大好きな空を日が暮れるまでボーッと眺め続けたり、外に飛び出して狭い路地を走り回る「スパイごっこ」に夢中になる日もあったそうです。
「『これをやる!』と心が動いたらその世界にギュウと集中」する性格は、現在の舞台への情熱にも通じています。
4歳の頃には、お姉さんの背中を追いかけるようにクラシックバレエを始めました。
この時も両親は縣千さんの選択を「いいね、楽しそうだね」と褒めて応援してくれました。
バレエは後に宝塚への道筋をつける重要な要素となりましたが、家族の温かい支援があったからこそ続けることができたのです。
宝塚との出会いは、バレエ教室の先輩に瀬奈じゅんさん主演の「Ernest in Love」のDVDを観せてもらったことがきっかけでした。
中学生の時に初観劇した宙組「TRAFALGAR/ファンキー・サンシャイン」に感銘を受け、音楽学校受験を決意します。
この時も家族は縣千さんの夢を全面的にサポートし、「最初で最後」と決めた受験で見事合格を果たしました。
5. 家族から受け継いだ価値観と現在
縣千さんの人格形成において、家族から受け継いだ最も重要な価値観は「素直さ」です。
この素直さがあったからこそ、宝塚入団後も多くの先輩方からの指導を真摯に受け止め、成長し続けることができました。
特に印象的なエピソードが、元雪組男役スター・香綾しずるさんとの関係です。
下級生の頃、縣千さんは自分から申し出て香綾しずるさんのお手伝いをさせていただいたのですが、香綾しずるさんがよく言ってくださったのが「縣色を大切に」という言葉でした。
縣千さんは「下級生の頃はガムシャラで、失敗したり、迷惑をかけてしまったり、本当にいろんなことをしでかしてしまったのですが、香綾さんはいつも温かい目で見守ってくださって」と振り返っており、香綾しずるさんの言葉を大切に受け止めています。
この「縣色を大切に」という言葉を素直に受け入れられたのも、家族から培われた価値観があったからこそでしょう。
縣千さんは「周りからいただいた言葉で私はできていると言っても過言ではない」と語っており、家族から学んだ謙虚さと感謝の心が現在も彼女を支えています。
現在も縣千さんは家族との良好な関係を維持しており、特に母親からの「自分のやりたいことをやりなさい。やり切ったかどうか考えなさい」という言葉を人生の指針として大切にしています。
宝塚という特殊な世界で活動する中でも、家族の存在が彼女にとって心の支えとなり続けているのです。
まとめ
縣千さんの魅力的な人格と現在の成功の背景には、温かく愛情深い家族の存在が不可欠でした。
母親から受けた「やりたいことをやりなさい。やり切ったかどうか考えなさい」という言葉、4歳年上のお姉さんから教わった人としての基本、そして家族全体で育んでくれた自由でありながらも責任感のある価値観。
これらすべてが現在の縣千さんという素晴らしい人格を形成しています。
芸名の由来となった「あがた祭り」に象徴されるように、縣千さんにとって家族との思い出は何物にも代えがたい宝物です。
好奇心旺盛で何事にも全力で取り組む姿勢、周囲の人々への感謝と思いやりの心、そして自分らしさを大切にする「縣色」の精神。
これらはすべて、家族から受け継いだかけがえのない財産なのです。
家族の愛情に支えられて成長した縣千さんの姿は、私たちに家族の大切さを改めて教えてくれます。
宝塚の舞台で輝く彼女を見るたび、その背後にある温かい家族の存在を感じることができるでしょう。
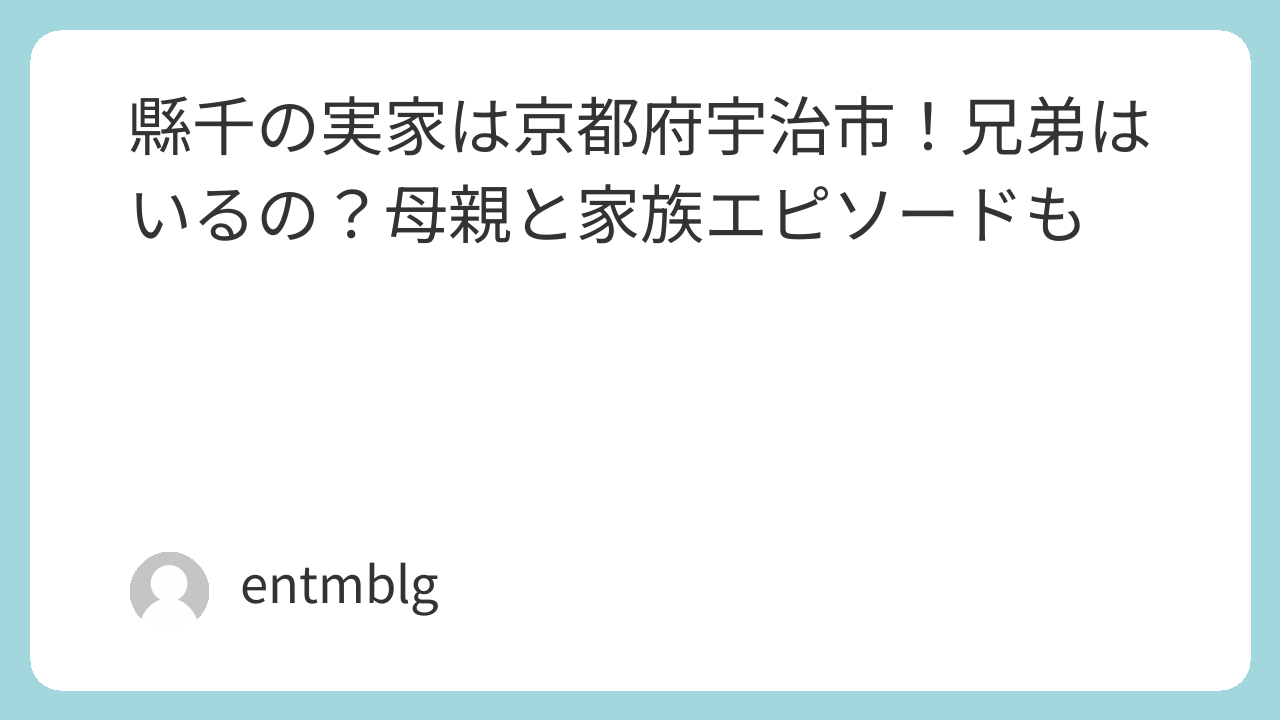
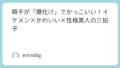
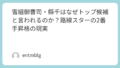
コメント