「七色の声をもつ歌の妖精」と称され、宝塚歌劇団で一時代を築いた涼風真世さん。
現在も美しい歌声で多くの人を魅了し続けている彼女ですが、宝塚時代の若い頃はどのような魅力を持っていたのでしょうか。
妖精のような美貌、透明感あふれる歌声、そして天真爛漫な性格で愛された涼風真世さんの宝塚時代を、貴重なエピソードとともに詳しくご紹介します。
涼風真世の宝塚入団から月組トップスターまでの軌跡
伝説の67期生として宝塚デビュー
1981年4月、宮城県石巻市出身の20歳の少女が宝塚の舞台に初めて立ちました。
それが涼風真世さんです。
第67期生として『宝塚春の踊り』『ファーストラブ』で初舞台を踏んだ彼女は、その後月組に配属されることになります。
この67期生、実は宝塚ファンの間では「美人の期」として今でも語り継がれているんです。
なぜなら、涼風真世さんと同期には、後に大女優となる黒木瞳さん(元月組トップ娘役)、真矢みきさん(元花組トップスター)、毬藻えりさん(元星組トップ娘役)など、現在も第一線で活躍する豪華なメンバーが揃っていたからです。
当時を知る人たちは「あんなに美人が集まった期は珍しい」と口を揃えます。
まさに宝塚史上屈指の黄金世代だったんですね。
そんな中でも涼風真世さんは、その独特な魅力で多くの人の心を掴んでいきました。
10年間の下級生時代で培った実力
宝塚では「研10」という言葉があります。
これは入団10年目という意味で、通常はこの頃までにはトップスターになるか、それが難しければ退団を考える時期とされています。
涼風真世さんがトップスターに就任したのは、まさにこの研10のタイミングでした。
この長い下級生時代、彼女は様々な役を演じながら着実に実力を積み重ねていきます。
1987年の『ミー・アンド・マイガール』でのジャッキー役では、その美しい歌声で観客を魅了。
また、1989年と1990年には『ベルサイユのばら』で憧れのオスカル役を演じる機会にも恵まれました(他組への特別出演として)。
「あの頃の涼風さんは、まるで本当にお姫様のようだった」と当時のファンは振り返ります。
10年という長い期間をかけて、彼女は確実に宝塚のスターとしての魅力を磨き上げていったのです。
1991年月組トップお披露目『ベルサイユのばら』
そして1991年、ついに涼風真世さんの時代が始まります。
月組トップスターとしてのお披露目公演は『ベルサイユのばら-オスカル編-』。
相手役には、後に大女優となる天海祐希さんがアンドレ役で出演していました。
この公演は、宝塚ファンの間では今でも「伝説の舞台」として語り継がれています。
涼風真世さんのオスカルは、まさに原作から抜け出してきたような美しさと気品を兼ね備えていました。
特に「我が名はオスカル」を歌う場面では、その透明感あふれる歌声に会場全体が息を呑んだと言われています。
「涼風さんのオスカルを超える人は、もう現れないんじゃないかしら」多くのファンがそう口にするほど、この公演での彼女の輝きは圧倒的でした。
ついに月組のトップスターとしての地位を確立した瞬間だったのです。
若き日の涼風真世の魅力と特徴
「七色の声をもつ歌の妖精」の美声
涼風真世さんといえば、何といってもその美しい歌声です。
「七色の声をもつ歌の妖精」という異名は伊達ではありません。
透明感あふれる澄んだ歌声は、聴く人の心を瞬時に別世界へと誘いました。
宝塚の男役といえば、通常は低く太い声で男性らしさを表現するものですが、涼風真世さんの歌声は全く違いました。
高音域から低音域まで自在に操る美声は、まさに天から授かった才能。
しかも、若い頃の彼女の歌声には特別な瑞々しさがありました。
「あの歌声を聞くと、自然と涙が出てきてしまう」「CDで何度聞いても、生で聞いた時の感動が蘇る」ファンからはこんな声が今でも聞かれます。
宝塚歌劇100年以上の歴史の中でも、これほど美しい歌声の持ち主は稀だったのではないでしょうか。
妖精のような美貌とフェアリータイプの魅力
涼風真世さんの若い頃の写真を見ると、本当に妖精のような美しさに驚かされます。
線の細い上品な顔立ち、透き通るような肌、そして何より印象的なのがその表情です。
どこか現実離れした、まさに「別世界の住人」のような雰囲気を醸し出していました。
面白いのは、舞台を降りた私生活では、レースやフリルをあしらった可愛らしい服装を好んでいたこと。
男役なのに、むしろ普通の女性よりも女性らしいファッション。
でも、いざ舞台に上がると、そんな可愛らしさが一転して凛々しい男役に変身するんです。
特に印象的だったのが、娘役との絡みで見せる独特の演技スタイル。
相手の目をじっと見つめるのではなく、少し視線を外しながら抱き寄せる仕草が何とも言えない魅力を醸し出していました。
「あの距離感がたまらない」と多くのファンが虜になったものです。
生活感のない神秘的な存在感
当時のファンがよく口にしていたのが「涼風さんは霞を食べて生きているんじゃないか」という言葉。
それほどまでに現実離れした、神秘的な存在感を持っていたんです。
宝塚の男役は通常、ある程度の「男らしさ」や「現実感」が求められるものですが、涼風真世さんの場合は全く違いました。
まるで本当に妖精の国からやってきたような、非日常的な魅力こそが彼女の最大の武器だったのです。
そのため、相手役となる娘役選びは毎回大変だったとか。
涼風さんよりも華奢で可憐な娘役を見つけるのは至難の業だったそうです。
でも、そんな困難すらも含めて、宝塚らしい「夢の世界」を体現していたと言えるでしょう。
宝塚時代の貴重なエピソードと人間関係
天真爛漫な性格が生んだ愛されエピソード
神秘的な舞台上の姿とは対照的に、素の涼風真世さんはとても天真爛漫な性格だったようです。
思ったことをポンポンと口に出してしまう性格で、それが時には可愛らしいエピソードを生み出していました。
有名なのが、相手役だった麻乃佳世さんとの稽古場でのやりとり。
『PUCK』の稽古中に「よしこ(麻乃佳世さんの愛称)って、心の綺麗な子じゃないよね」とストレートに言ってしまい、麻乃佳世さんを号泣させてしまったというエピソードがあります。
もちろん悪気があったわけではなく、思ったことをそのまま口にしてしまう天真爛漫さゆえのこと。
また、同期の家に遊びに行った帰りに、そのまま玄関で寝てしまったという話も。
その寝顔があまりにも可愛らしくて、怒る気になれなかったというから、やはり特別な魅力があったのでしょうね。
67期生の強い絆と支え合い
67期生の絆の深さは、宝塚史上でも特別なものでした。
特に1985年の日航機墜落事故で同期の吉田由美子さん(北原遥子)を失った悲しみは、残された仲間たちの絆をより深いものにしました。
黒木瞳さんは当時こんな言葉を残しています。
「同期に励まされ、誰一人欠けても同期じゃないっていう風にみんな思っていると思う」
涼風真世さんも、仲間の死を受けて御巣鷹山を訪れたことがあります。
女優としてどう生きていくかを問いかけたくなったためだそうです。
「背中を押してもらったような気がする」と後に語っているように、亡き友への思いが彼女の人生にも大きな影響を与えています。
現在も67期生の絆は続いており、それぞれが違う道を歩みながらも、お互いを支え合っています。
代表作に見る若き日の輝き
涼風真世さんのトップスター時代の代表作を振り返ると、その多彩な魅力がよく分かります。
『銀の狼』では記憶を失った医師シルバを演じ、銀色の髪が印象的でした。
麻乃佳世さんとのラストシーンで新しい生活を始めるために旅立つ姿は、とても幻想的で多くのファンの心に残っています。
『PUCK』は、まさに涼風真世さんのために書き下ろされた作品。
妖精パックを演じる彼女は、まさに適役中の適役でした。
この作品は後に月組で再演されていますが、やはり涼風さん以外では物足りないという声も多く聞かれます。
そして退団公演となった『グランドホテル』。
余命宣告を受けた男オットーを演じた涼風さんは、生きることの美しさを歌声と演技で表現しました。
多くのファンがハンカチを手放せなかった、感動的な舞台だったそうです。
どの作品でも共通しているのは、涼風真世さんならではの透明感と美しさ。
若い頃の彼女だからこそ表現できた、かけがえのない輝きがそこにはありました。
まとめ
涼風真世さんの若い頃は、まさに宝塚歌劇が追求する「夢と美の世界」を体現した存在でした。
妖精のような美貌、七色の声と称された歌唱力、そして天真爛漫な人柄で、多くの人々に愛され続けました。
67期生という豪華な同期に恵まれながらも、独自の魅力で月組トップスターまで上り詰めた彼女の軌跡は、宝塚の歴史に燦然と輝いています。
10年という長い下級生時代を経てつかんだトップの座、『ベルサイユのばら』での伝説的なオスカル役、そして数々の名作での輝き。
すべてが若き日の涼風真世さんだからこそ生み出せた、かけがえのない宝物です。
現在も「むかし妖精、いま妖怪」と自虐ネタで笑いを取る彼女ですが、その美しい歌声は変わらず、多くの人々に夢と感動を与え続けています。
若き日の輝きを知ることで、現在の涼風真世さんの魅力もより深く理解できるのではないでしょうか。
宝塚が生んだ真の「歌の妖精」、涼風真世さんの若い頃の魅力は、これからも多くの人の心に生き続けることでしょう。
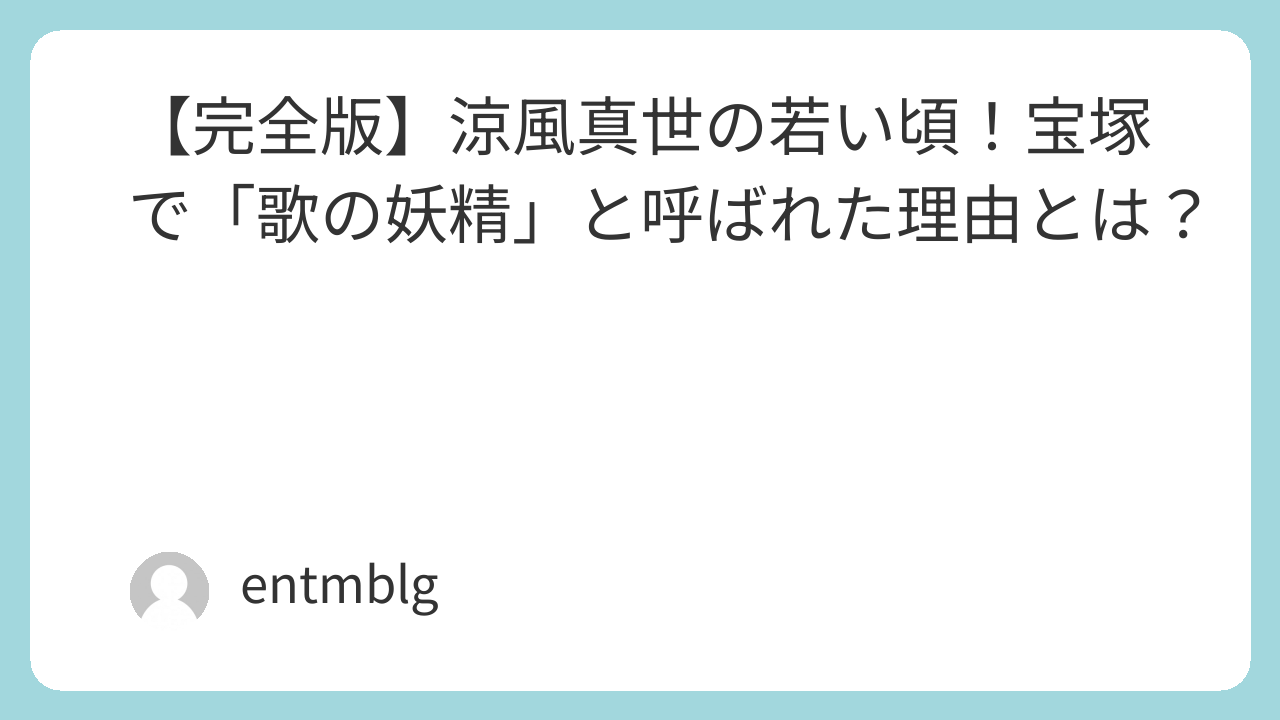
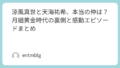
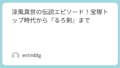
コメント